低糖質ダイエットに絶対欠かせない食物繊維の役割とは?

低糖質ダイエットは、現在日本で主流となっているダイエット法のひとつです。
基本は糖質を減らしタンパク質を摂ることですが、実は「食物繊維」が非常に重要な役目を担っていることがわかってきました。
今回はそんな低糖質ダイエットについて、食物繊維はどのような働きをするのか、そして、どうして食物繊維が必要なのかについて、詳しく解説をしていきたいと思います。
思わぬところでダイエットに失敗したり、痩せずに悩んでいる方は必見です!
このページの目次を
炭水化物と糖質・食物繊維の関係
低糖質ダイエットと食物繊維について解説をする前に、まずは「炭水化物」「糖質」「食物繊維」の関係について見ていきましょう。
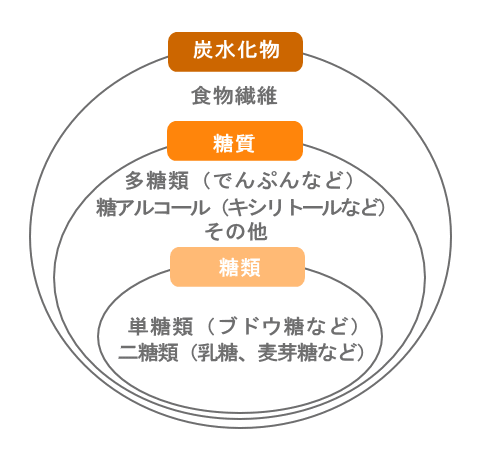
炭水化物とは
炭水化物とは、植物の「光合成」によって作られる栄養素です。「タンパク質」「脂質」と並ぶ三大栄養素のひとつで、生命活動をするうえで欠かせない重要な栄養素となっています。
炭水化物は「糖質」と「食物繊維」に分類することができます。つまり、糖質と食物繊維の総称を炭水化物と呼びます。炭水化物と糖質はほぼ同じ意味で使われていますが、厳密には違うので覚えておきましょう。
糖質とは
糖質は炭水化物の一種ですが、さらに「単糖類」「二糖類」「糖アルコール」「デンプン」などに分類することができます。それぞれ形は違いますが、体内でエネルギーとなる「ブドウ糖」に分解されます。
ブドウ糖は人が生きるためのエネルギー源で、特に脳の活動に大きな影響を与えると言われています。ブドウ糖が不足すると、脳や体がエネルギー不足となり、体調不良を起こしてしまう可能性があります。
糖質は、味覚を刺激して甘さを感じさせる働きもあります。代表的なのは「砂糖」で、その約99%が糖質でできています。糖質ダイエットは「糖質を制限して痩せる」ダイエット法のことですが、甘いお菓子やデザートを我慢できるかどうかが重要です。
食物繊維とは
食物繊維も糖質と同じく炭水化物の一種です。植物の光合成によって生成されますので、肉類や魚類には含まれません。食物繊維の大きな特徴として「人の消化液で消化されない」ということが挙げられます。
食物繊維は水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」に大別することができます。水溶性は「繊維状」ではありませんが、人の体内に吸収されないという特徴から「繊維」と名づけられています。
食物繊維の主な働きは以下の通りです。
- 便秘を予防する
- 腸内の老廃物を排出する
- 血糖値の急な上昇を防ぐ
- 満腹感を感じさせる
- 虫歯を予防する
ほかにも、大腸がんや静脈瘤(じょうみゃくりゅう)の予防など、健康に欠かせない働きをする重要な栄養素です。
食物繊維が不足しがちな低糖質ダイエット

低糖質ダイエットをしていると、食物繊維が不足しやすくなります。どうしてそのようなことが起こるのか、低糖質ダイエットの特徴を確認し、その謎を紐解いていきましょう。
低糖質ダイエットの基本知識
人が太る原因は「糖質」の摂りすぎだと言われており、それを制限することで痩せようとするのが「低糖質ダイエット」です。「炭水化物制限ダイエット」「糖質制限ダイエット」「ローカーボダイエット」などと呼ばれることもあります。
糖質は人のエネルギー源となるので、それを制限すると、体がエネルギー不足となってしまいます。そこで代わりのエネルギー源となる「タンパク質」や「脂質」で、その不足を補う必要があるのです。
従来のダイエット法では、お肉や脂ものなど「高カロリー食」の制限が基本でした。しかし低糖質ダイエットでは、タンパク質や脂質を摂るために高カロリーの食事をすることもあります。
低糖質ダイエットは食物繊維が不足する
低糖質ダイエットをしていると、どうしても食物繊維が不足してしまいます。その理由は、低糖質ダイエットの食事法にありました。
低糖質ダイエットの基本は「糖質を制限」し、お肉や魚などの「タンパク質」でエネルギーを補充することです。しかし食物繊維は「植物」の光合成で生成される栄養素なので、お肉や魚には一切含まれていません。そのような食事を続けていれば、自然と食物繊維が不足してしまうのです。
しかしお肉や魚だけでなく、野菜・キノコ類・乳製品・豆類など、栄養バランスを考えて食べることができていれば、食物繊維不足にはなりません。しっかり意識して食事を摂らないと、「食物繊維が不足しやすいダイエット方法」だということを知っておきましょう。
ダイエットや健康維持に食物繊維が必要な理由

食物繊維は人の体では消化できず、吸収もされません。一昔前まで「人には不要な栄養素」だと言われており、その重要性が見直されてきたのはごく最近のことなのです。
ではどうして食物繊維が必要なのか、不足するとどうなってしまうのか、詳しく見ていきましょう。
水溶性食物繊維の働き
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維では、その役割が少し異なります。まずは水溶性食物繊維の主な働きを確認しましょう。
- 排便を促す働き
- ブドウ糖の吸収を抑える(血糖値の上昇を抑える)
- コレステロールの吸収を抑える(動脈硬化の予防)
- ナトリウムを排出する(高血圧の予防)
- 満腹感を得る働き
便がたまっていると、腸内の働きが悪くなり、消化吸収が妨げられるため、体が脂肪をためやすくなってしまいます。食物繊維は排便を促し、腸内環境を整える働きがあるため、ダイエット中はしっかりと摂っておきたいところです。
さらにブドウ糖の吸収を抑えることで、肥満ホルモンと呼ばれるインスリンの分泌をゆるやかにすることができます。粘着性があり腸内をゆっくり移動するため、満腹感を得てお腹がすきにくいという特徴もあります。
不溶性食物繊維の働き
次は、水分に溶けることがない「不溶性食物繊維」の働きを確認しておきましょう。
- 排便を促す働き
- 咀嚼力の強化
- 虫歯予防
- 満腹中枢を刺激する働き
- 大腸がんの予防
- 痔の予防
- 静脈異常の予防
水溶性と同じく、排便を促すことで、体内の有害物質を排出する働きがあります。さらに不溶性食物繊維を含む食材は噛み応えのあるものが多く、咀嚼力の強化や虫歯予防にも役立ちます。
噛む回数が増えることで満腹中枢が刺激されるため、ダイエットの効果も高めてくれるでしょう。
食物繊維が不足するとどうなる?
食物繊維はダイエットや健康維持に必要な栄養素ですが、もし不足すると具体的にはどのようなことが起こってしまうのでしょうか。
まず一番大きな影響は、腸にあらわれます。食物繊維が不足すると便が硬くなり、便秘になってしまいます。便秘は腸内の消化吸収を妨げてしまうので、ダイエットの大きな障害となります。
食物繊維は血糖値の上昇を抑える効果があるので、これが不足すると血糖値が上がりやすくなってしまいます。血糖値が上がると、肥満ホルモンと呼ばれるインスリンが分泌されます。インスリンは血中の糖をどんどん運び出し、細胞が受け取れなかった糖は体脂肪として蓄えてしまうのです。
食物繊維を摂っていれば、血糖値の上昇がゆるやかになり、インスリンの分泌も抑えられます。するとインスリンは時間をかけて糖を運び出すので、細胞がしっかりと糖を受け取り、エネルギーに変換してくれるのです。
オススメ 糖質制限ダイエットや置き換えダイエットに必要な食物繊維はおいしい青汁が有効
低糖質ダイエットにおすすめの食事法
低糖質ダイエットをするなら、正しい方法で行うことをおすすめします。間違った方法でダイエットを続けていると、痩せないだけでなく、リバウンドしたり、体を壊してしまったりすることもあります。
まずは正しいやり方の確認と、おすすめの食事法をご紹介します。
糖質の摂取量を調整する
低糖質ダイエットで一番大切なのは、糖質の摂取量を減らすことです。そのためには、どの食材にどれほどの糖質が含まれているか、ある程度知っておく必要があります。
例えば、白ご飯なら1杯で約50g前後の糖質、食パン1切れで25~30g、小麦粉大さじ1杯で約7gなど、食材によって糖質量は大きく異なります。せっかく白ご飯を抜いて糖質を減らしていても、自分が気付かないところで糖質を摂ってしまっていたら、もったいないですよね。
そのためにも、まずは食材ごとの糖質をチェックするクセをつけ、こまめに糖質量を管理することをおすすめします。
オススメ記事:こんなにあるんだ!低糖質の食品【糖質制限の基礎知識】
糖質摂取量の目安

食材の糖質量をチェックしたら、それを1日にどれだけ摂取するか決めましょう。一般的な成人男性なら、1日に約300~400g程度の糖質を摂取しています。もし低糖質ダイエットをするのであれば、まずは1日150gからはじめてみましょう。
1週間ぐらいで体を慣らしたあと「まだまだ余裕がある」「しっかり痩せたい」と考える人は、1日に60~100g程度まで減らしてみましょう。ただし1日150gでも正しい方法で行えばきちんと痩せることはできるので、無理をせずに継続することも大切です。
タンパク質でエネルギーを補充する
糖質を減らしていると、カロリー(エネルギー)不足になってしまいます。カロリーは人が生きていくうえで必ず必要になるもので、不足すると体調を崩してしまいます。
特に糖質制限をしているときは、タンパク質や脂質をしっかりと摂ってカロリー補充をする必要があるのです。ちなみに、これは覚える必要はありませんが、カロリーは糖質・タンパク質・脂質にだけ含まれています。
つまり低糖質ダイエット中の食事は、お肉や魚などのタンパク質食材がメインとなります。
栄養バランスを考える
糖質とタンパク質の基本を押さえたら、ほかの栄養素にも目を向けてみましょう。お肉や魚だけではビタミンやミネラル、食物繊維が不足しますので、野菜・豆類・キノコ類・乳製品などもバランスよく摂取しなければいけません。
その中でも低糖質ダイエットに一番ぴったりな食材は、大豆製品です。大豆は「植物」なので、食物繊維が豊富に含まれています。さらに肉類に匹敵するほどのタンパク質も含まれており、低糖質ダイエットでは欠かせない食材となっています。
オススメ 糖質制限ダイエットや置き換えダイエットに必要な食物繊維はおいしい青汁が有効
食物繊維の摂りすぎには注意しよう

健康維持のためには食物繊維の摂取は欠かせませんが、摂りすぎも体に良くありません。どれぐらいの量がちょうど良いのか、目安を確認しておきましょう。
食物繊維の目安摂取量
厚生労働省が発表する「日本人の食事摂取基準」によると、食物繊維は1日に約20g程度摂取する必要があるということです。実はほとんどの日本人がこの量に到達しておらず、慢性的な食物繊維不足に陥っているのです。
具体的な食物繊維量の例を挙げますので、参考にしてください。
- バナナ1本:約1.7g
- ほうれん草80g:約2g
- 納豆1パック:約2.7g
- おにぎり2個:約0.6g
- ゴボウサラダ1食:約1g
- りんご1個:5g
- キャベツ100g:約1.8g
このように見てみると、食物繊維が豊富な食材を意識して摂らないと、1日20gはなかなか達成できません。キャベツなど、食物繊維が豊富と言われている野菜でも100g中1.8gしか摂取できないのです。
低糖質ダイエットをする・しないに関わらず、普段からできるだけ意識して食物繊維を摂るようにしておきましょう。難しければ、サプリメントでの補充も視野に入れていいかもしれません。
食物繊維のバランス
食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があると言いましたが、この2種類の摂取バランスも大切です。
あまり意識しすぎる必要はありませんが、水溶性1に対し、不溶性が2のバランスが最適だと言われています。例えば食物繊維含有量が非常に優秀な「納豆」は、100gあたり水溶性が2.3g、不溶性は4.4gも含まれていますが、これはとても良いバランスですよね。
ブロッコリーは100g中、水溶性が0.7g、不溶性が3.7g含まれています。食物繊維の含有量で言えば優秀ですが、こうして詳細を見ると水溶性が少ないことがわかります。食物繊維を摂るときは、このバランスにも注意して摂取してみましょう。
食物繊維を摂りすぎると何が起こる?
食物繊維が不足すると体に悪い影響が出てしまいます。しかし、食物繊維の摂りすぎもまた健康に良くありません。食物繊維を摂りすぎてしまった場合、一体どのようなことが起こるのでしょうか。
便秘
食物繊維を摂ることで便秘の解消につながると言いましたが、実は食物繊維の摂りすぎで逆に便秘になることもあります。
不溶性食物繊維は、水分を吸収して膨らむことで、腸内に刺激を与えて便秘を解消します。しかし不溶性食物繊維を摂りすぎると反対に便が硬くなり、便秘になることがあるのです。
食物繊維をしっかり摂っているのに便秘が解消されない、または便秘が悪化しているという場合は、不溶性食物繊維を摂りすぎている可能性があります。そんなときは、不溶性食物繊維の摂取を一時的に控え、水溶性食物繊維を積極的に摂るようにしてみましょう。
下痢
便秘になることもあれば、下痢になってしまうこともあります。食物繊維を摂ると、腸内が刺激され、排便が促されます。しかし食物繊維を摂りすぎることで、腸内の運動が活性化しすぎて、反対に下痢になってしまうのです。
「便秘よりはマシ」と思うかもしれませんが、下痢は体力を激しく消耗しますし、何よりビタミンやミネラルが便と一緒に流出してしまう可能性もあります。必要な栄養素が流れ出てしまうので、栄養を摂っていても「栄養不足」の状態になってしまうことがあるのです。
腹痛
食物繊維の摂りすぎで起きる腹痛は、いくつか原因があります。ひとつめは、便秘による腹痛です。便がたまっていることにより、腸内が膨張し、組織が圧迫されることで腹痛が発生します。反対に下痢の状態でも、腸内活動が活発すぎて腹痛を起こしている可能性があります。
ほかにも、腸内に便が溜まることで有毒ガスが発生し、腹部の膨張などで腹痛を起こすことがあります。そのガスは便によって出口がない状態になっていると、血液中に取り込まれて全身に運び込まれるため、健康に悪い影響を及ぼします。
さいごに
いつも通りの食事をしていても、食物繊維は不足しがちな栄養素です。
そのうえ食物繊維の豊富な穀物(ご飯や小麦粉)や根菜、イモ類などを制限する「低糖質ダイエット」を行うと、ほとんどの方が食物繊維不足に陥ります。
納豆や葉物野菜など、糖質が少なく食物繊維の多い食材をなるべく選び、積極的に摂取するように心がけましょう。
難しいようならサプリメントでの摂取も視野に入れ、不足しないように注意しながらダイエットに取り組みましょう。
